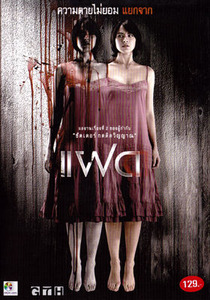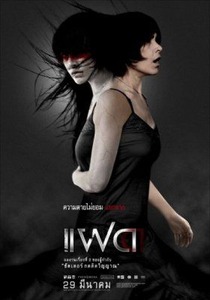日本の42歳(2010年現在69年生41歳)
182万7000人
2010年現在世界の人口
中位年齢39.7歳(先進国内)
総人口12億3722万8000人
15歳未満+65歳以上=34.5%
2005年統計
35~39歳 4億6585万1000人
中位年齢が40歳に到達する年次
既に到達した国
日本・イタリア1990年代
ドイツ2000年
フランス・スペイン・オランダ・ギリシャ・ベルギー・スウェーデン2010年
開発途上国 2050年以降
韓国・ウクライナ2010年代
中国・アメリカ2030年
インドネシア・トルコ・アルゼンチン2050年
ブラジル・メキシコ・ベトナム・イラン・タイ2040年
ロシア・イギリス・カナダ2020年
オーストラリア2020年代
45歳(66年生44歳)
174万6000人
44歳(67年生43歳)
181万7000人
在留邦人
113万1807人
帰国日本人数
278万2785人
国籍別登録外国人数 平成21年
218万6121人
丙午(ひのえうま)年(昭和41年)生まれの人
新成人となった昭和62年(136万人)
平成14年36歳 135万人
http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20091014#p1
2009-10-14 なぜ丙午の年に乳児死亡率が高いのか
『人間万事塞翁が丙午』(にんげんばんじさいおうがひのえうま)は、青島幸男作の小説。著者の母をモデルとしている。書名は主人公ハナが
丙午に生まれたことによる。戦中から戦後にかけての下町の生活を、講談調で記述している点に特徴がある。タイトルは中国の古書「淮南子」
に書かれている故事「人間万事塞翁が馬」のパロディ。
1981年第85回直木賞受賞作品。1982年にTBSによりテレビドラマ化された。
なお、本作には以下の様な特徴がある。
直木賞を取ると周囲に公言して執筆を始めた作品
小説としては処女作
処女作での主要文芸賞の受賞
作者の最初で最後の小説作品(他の著書はエッセイ・随筆のみ)
このような要素が重なった作品は日本の文学史を見渡しても他に無く、「超マルチタレント」とも称された青島の優れた才能の一端を示すエピ
ソードとして知られる。
あらすじ [編集]
--------------------------------------------------------------------------------
注意:以降の記述で物語・作品・登場人物に関する核心部分が明かされています。免責事項もお読みください。
--------------------------------------------------------------------------------
呉服問屋が並ぶ東京日本橋の堀留町にある仕出し弁当屋「弁菊」が舞台となっている。主人公ハナは21歳のときに、人情味あふれるにぎやかな
下町に嫁いだ。そして夫の次郎とともに謙一、幸二の二人の息子を育て上げる。また様々な事件に遭遇するが、持ち前の明るさとたくましさで
乗り越えていく。
夫の次郎に召集令状が届き従軍、復員、再召集、帰還、そして戦後に旅館業を営み次郎が亡くなるまでを描く。
塞翁が馬 【意味】 塞翁が馬とは、人間の吉凶・禍福は変転し、予測できないことのたとえ。また、だから安易に喜んだり悲しむべきではない
ということ。「人間万事 塞翁が馬」とも。塞翁がうま。
塞翁が馬の「塞翁」とは、北方の「砦・塞(とりで)」に住むとされた老人(翁)のことで、出典は中国前漢時代の思想書『淮南子(えなんじ
)』「人間訓」の以下の故事から。 昔中国の北方の塞に占いの得意な老人(塞翁)が住んでいた。 ある日、塞翁が飼っていた馬が逃げてしま
ったので、人々が慰めに行くと、塞翁は「これは幸いになるだろう」と言った。 数ヵ月後、逃げた馬は立派な駿馬(しゅんめ)を連れて帰っ
てきたので、人々がお祝いに行くと、塞翁は「これは災いになるだろう」と言った。 塞翁の息子が駿馬に乗って遊んでいたら、落馬して足の
骨を折ってしまったので、人々がお見舞いに行くと、塞翁は「これは幸いになるだろう」と言った。 一年後、隣国との戦乱が起こり、若者た
ちはほとんど戦死したが、塞翁の息子は足を骨折しているため兵役を免れて命が助かった。この故事から、「幸(福・吉)」と思えることが、
後に「不幸(禍・凶)」となることもあり、またその逆もあることのたとえとして「塞翁が馬」と言うようになった。 また、「人間のあらゆ
ること(人間の禍福)を意味する「人間万事」を加えて、「人間万事 塞翁が馬」とも言う。
http://1bandiary.seesaa.net/article/147952974.html
「塞翁之馬」
の出典を調べていましたら、
中国前漢時代の哲学書「淮南子(えなんじ)」の
「人間訓(じんかんくん)」が出典と知りました。
「人間」を「じんかん」と読む場合は、
「世間、人の住んでいる場所」を意味するようです。
この出典からすれば、「じんかん」と読むのが正しいように
思いますが...
青島幸男作の小説
『人間万事塞翁が丙午』は
(にんげんばんじさいおうがひのえうま)
と読むようです。
この小説を離れて、「故事」として考えても
辞書などによれば「にんげんばんじ~」というのが
正しい読み方のようです。
似たような例として、
「人間到る所青山あり」
は本来「じんかんいたるところせいざんあり」
と読むのが正しかったのですが、
最近は事情が変わってきているようで、
『大辞泉』などでは、
「じんかん」の項目は見出しとしてはありますが
「⇒にんげんいたるところせいざんあり」となっていて、
「にんげん」が一般的と判断しているようです。
「人間万事塞翁が馬」の場合も同様の流れをたどった
可能性はあります。
ところで、小説「人間万事塞翁が丙午」は、
呉服問屋が軒をつらねる東京の下町、日本橋堀留町。
人情味豊かであけっぴろげ、良くも悪くもにぎやかな下町に、
21歳で嫁いできたハナは、さまざまな事件に出会いながらも、
持ち前のヴァイタリティで乗り切ってゆく内容です。
戦中から戦後へ、激動の時代をたくましく生きた庶民たちの哀歓を、
青島、自らの生家をモデルに著者の母を主人公としたといいます。
講談調で記述している点に特徴があります。
19年前、TBS系で放送されていた「人間万事塞翁が丙午」。ケーブルテレビで再放送
チャンネルNECOさんから「再放送は出来ません」って言われてしまったんです・・・。
http://amamori.exblog.jp/1332517/
これは昭和55年~56年に「小説新潮」に連載され、昭和56年に直木賞を受賞した青島幸男さんの作品です。
「ぴいひゃらどんどん」「繁盛にほんばし弁菊」 に続く青島さんのルーツ三部作の最終巻となります。ですから青島さんも、幸二という名前で登場します。彼は、ご幼少の砌、虚弱な子供で胸を患ったりして、25才まで保てば、それ以降は丈夫になるなどと言われたりしていたようです。
さて、主人公は、謙一、幸二兄弟の母、ハナさんです。(↑の系図を参照下さい。)父の次郎さんも出ますが、なんといっても主役はハナさんです。幸二達からは祖父母にあたる謙二・こう夫婦は、もうすっかりご隠居さんです。この夫婦の代に始まった、仕出し弁当屋の”弁菊”も、日本橋堀留町で大繁盛しているのですが、これを実際に切り盛りしているのはハナさんなんです。あまり活躍しない亭主の次郎さんは、兵隊としては優秀だったらしく、支那事変(日中戦争)にも召集されてしまう。(戦争末期にも、また召集される。)
昭和20年に入り、日本本土への空襲が激化し、延焼防止のため弁菊は取り壊されてしまう。
そして戦後、弁菊のあった場所の近くで、今度は旅館を始める。祖父母は弁菊の名に拘ったが、主役は名実共にハナさん。”花屋旅館”の看板を掲げることになった。場所が良くて、この旅館も繁盛するが、女中頭が辞め、自分ですぐ近くに旅館を開業して、花屋旅館の客を奪ったり、次郎さんが浮気をしたり、そして52才で若死にしたり、丙午のハナさんの苦労の種は尽きない・・・ 05.7.13読了 1981新潮社・刊 ¥880

 ramapie,St.Family@ramapie
ramapie,St.Family@ramapie きんたたたたん@kinta_mizu
きんたたたたん@kinta_mizu yona@yona1127
yona@yona1127 姉@おで光成全力待機@live48ane
姉@おで光成全力待機@live48ane

























![[閉じる]
萌える! プロレスのススメ 力石ほたるVSちはたん2号 ジャーマンスープレックスVer.(フィギュア) 商品画像1](http://www.1999.co.jp/itbig06/10064432a.jpg)